その1は以下からご覧ください。

続きを見ていこうと思います。
製造部門について
製造部門は行政処分以前では、手順書と製造工程、実作業が必ずしも合致していませんでした。ただ、現場は品質に影響が生じるものではない、手順書からは逸脱するが、承認書との相違がない、逸脱処理が必要な案件ではないという発想にならず、問題がある事案であるという認識がなく、点検時や、行政処分時のヒアリングでも検出されなかったとのことです、
中にはA氏に報告された事案があったみたいですが、逸脱処理が必要との発送にならなかったものもあったみたいです。しかし、いずれにしても品質保証部門への報告はなかったようです。
結局のところ、管理機能が不十分であったといえそうです。これは1回目の行政処分があった後、川内工場の指摘が限定的であったことから、重大な問題はないと捉えた者がいたとのことです。
また、上層部からの製造部に対して法令遵守をした製造行為を徹底するのではなく、逸脱処理、変更完了を経ずに手順と異なる作業を実施するよう指示されたため製造部門の作業員は行政処分以前から変わらないと印象づけられたため、法令遵守の意識が薄れていったようです
なぜ不適切な行為が行われたか
なぜ、行政処分以降も不適切な事案が行われていたのでしょうか。
理由の1つとして川内工場ではセフェム系の抗菌薬を製造していたことが挙げられています。
まず、セフェム系を含む抗菌薬はここ数年供給が不安定であったという前提があります。
その抗菌薬の需要が拡大しており、生産の逼迫及び供給に関する受託元からのプレッシャーなどがあったことは想像に難くありません。この背景から、A氏は生産を優先するという判断をしたようです。
コロナ禍後に全世界的にセフェム系抗菌薬の需要が急激に増加したこと、欠品を生じれば委託先からの信用を失い、受託契約が打ち切られるという不安、ほかの2工場では法令遵守の徹底に重きを置いたことで生産量が大幅に減少していたこと、川内工場が大きな利益を上げている状況が続いているいたこととさまざまな要因にが絡み合っています。ここで、このプレッシャーの中で正常な判断が下せるかというと・・・。
もちろん、GMP、法令を蔑ろにして生産を優先するという判断は擁護できるものではないです。
が、同じ立場にもしいたらと思うと・・。正直、生産を優先したくなる気持ちもわからんでもないです。
責任役員はどうしたか
経営方針については基本的に責任役員の管轄ではあると思います。じゃあこの件についてどうしていたかというと、受注制限を指示を出したようです。また、製造委託元の代表者との間で受注量を減少させる旨の協議を行なっていたりなど、生産量の適正化に向けた検討を行なっていたそうです。
役員から見ても過剰であったという認識みたいですね。どこまで把握できていたかは気になりますが、ある程度現場の実情を理解していたように思います。
しかし、A氏は制限について具体的なアクションを起こさず、役員への相談、方向もなく、人員の補充がされれば生産に継続が可能との発言に終始していたようです。また、作業時間を短縮したいという思いから手順書と異なる手順での作業が行われた事案があったとのことです。
前回の記事で書いたようにA氏は優秀な人であったと言われています。そんな人がさまざまなプレッシャーの中で正常な判断を下すことができなくなったこと、プライドが邪魔したのか、頼れる人が近くにいなかったためか相談、報告することがなかったというのが本件の問題点の1つであると感じます。
やはり、同じぐらいの知識量を持つ人員が複数人いないと、間違った方向に行った時に修正できないものなのでしょう。そう行ったことも含め、教育は必要ですね。
次は2021年の行政処分後の改善効果について見ていこうと思います。
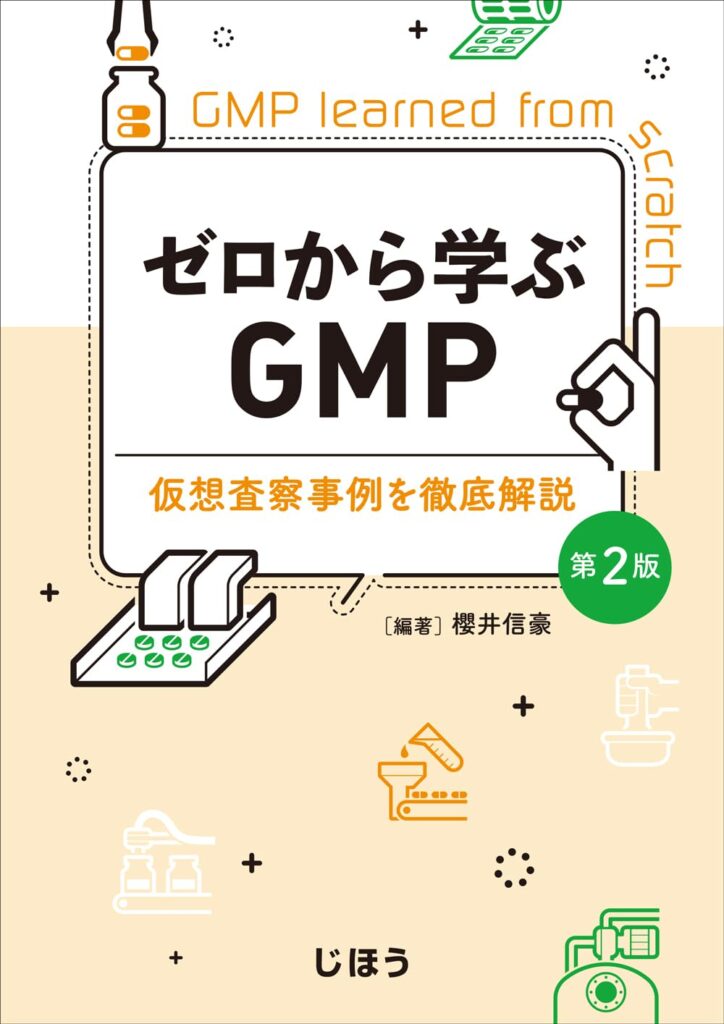
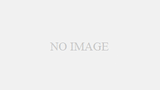
コメント