長生堂製薬が行政処分を受けたようです。2021 年 10 月に徳島県より受けた業務改善命令に対する改善を推進中のところ、製造・品質関連業務を適切に行わなかったこと等を理由として行われたとのことです。報告書は以下のURLからご確認ください。
https://www.choseido.com/news/pdf/250327.pdf
報告書で感じた点をまとめてみます。
概要
長生堂には3ヶ所工場あり、今回対象となったのは川内工場です。
2021 年 10 月 に本社工場、本社第二工場及び川内工場と全ての工場が業務停止処分及び業務改善命令を受けています。今回、業務改善を推進している中で、川内工場において製造管理上の不備がある旨の社内報告を受け、 調査した結果、 川内工場の製造工程において承認書に記載のない追加乾燥を行った事案等、逸脱処理を適切に実施していない事案が複数存在することが判明し、改善計画に基づく取り組みが川内工場において不十分であることが確認されたためとのことです。報告書をみて感じたことを書いてみます。
2021年の行政処分前の体制について
2021年の行政処分の時は1品目を除き、重大な齟齬が発見されていませんでした。この理由として挙げられているのは、品質保証部門の管理機能が一定程度発揮されていたからとされています。
ただ、工場長が配置されておらず、代理であったA氏が実質的な工場長としての役割をもっており、A氏は製剤および包装のいずれの技術面について広い知見をもっており、工場内で同等以上の知見を持つものが不在、限られていたとのことです。
また、高い知見を持つA氏に何かあれば聞けばよいという共通認識があったとのことでA氏に頼りきりだった印象を受けました。A氏は品質保証部門ではないですが。
ただ、A氏にきた報告のうち、製造上、重大な事案と判断した場合はB氏に相談されていたようです。
B氏は川内工場の製造管理者兼品質管理部長で品質保証業務に対し深い知見をもっていたそうです。
また、他の課員の品質保証業務のサポートや最終確認を行なっており、他にも製造部門からの報告や相談を行いながら逸脱処理をすることもされてたそうです。
また、2019年8月ごろ、処分を受ける前に承認書、手順書の記載と製造の実態との齟齬を確認しており、齟齬があれば改訂を行なっていました。
この時点では他工場よりも対応が進んでいました。
まず、工場長がいない点が気になりました。工場を実質的にA氏が役割を担っていたとはいえ工場全体を統括する人がきちんと設置されていないのはどうなんでしょうか。
また、A氏およびB氏の役割が大きく、2人に頼りきりな印象を受けます。とはいえ、管理能力が発揮されており重大な不適切行為の発生は防止されてたと評価されています。
少なくともこの時点ででは、大きな問題はあまりなかった(表面化していなかった)といえます。
その土台がA氏、B氏という柱で支えられており、代わりがいないですが。
2021年行政処分以降
2021年に行政処分を受け、業務改善を会社として推進していくことになります。
特に本社工場、本社第二工場の品質保証体制の早急な強化が急務でした。
川内工場が相対的に管理機能が機能していたこと、人的リソースの制約があったこともあり、B氏を本社工場へと配置転換しました。
その結果、川内工場は2つあった柱を1つ失ったと言えるでしょう。
一応、代わりの製造管理者が着任しましたが、品質保証に関する知見や経験がB氏と比べ豊富でなかったとのことです。
また、B氏の交代でサポートが受けられなくなったため、知識、能力不足が顕在化し、品質保証部門による製造部門に対する監査が十分な状態ではなくなったとのことです。
このような状況でB氏が行なっていた品質情報報告書の確認、逸脱報告の確認などA氏が担うことになったようです。
また、各工場の逸脱処理への考え方のすり合わせを目的として、逸脱確認会を毎週開催し、共有が図れれていたが、川内工場では逸脱件数が少なかった。
この少ない理由として、扱う品目の製剤特性に起因するものであるとの認識で、適切な処理がされているかを十分に検証されていなかった。そのため、管理機能が十分に発揮されていなかったようです。
品質保証部門への報告
逸脱の報告は基本的に品質保証部門に行われるものと認識していますが、B氏に頼りきりであったため、B氏が異動後は製造から品質保証部門に報告が上がらなくなってしまい、A氏にその分が流れていったようです。
製造部門の気温的な部分から説明する必要があることがその理由として挙げられてるんですが、これ品質保証部門な製造現場に出向いていないということでは?やはり、常日頃から現場にで向いてコミュニケーションをとることが必要でしょうね。
結局A氏も処理に時間がかかるとの懸念から製造現場で問題が起きれば品質保証部門をではなく、A氏に報告するように示唆したとのことです。
A氏が工場内で信頼されていた、影響力が大きいために起こったワンマン体制とも言えるでしょうか。
その結果、品質保証部門の機能は著しく低下してしまったといえるでしょうか。
B氏はその後の異動で川内工場に復帰していますが、復帰後も継続されていたとのことです。
まとめ
ここまでをまとめると、比較的、管理機能が一定程度機能していたが、その実情はA氏、B氏といった特定の人に依存した体制であり、そこに気づいていなかったため、B氏の異動によって管理体制が脆弱になり、またそれを是正することができなかったとように思います。
特定の人に依存する体制は脆いということと、後任への技術、知識の継承というのが非常に重要であること、品質保証部門と製造部門の連携が取れてないと必要な対応が取れないということでしょうか。
まだ、報告書には見るべき部分があるので、また記事にしようかと思います。
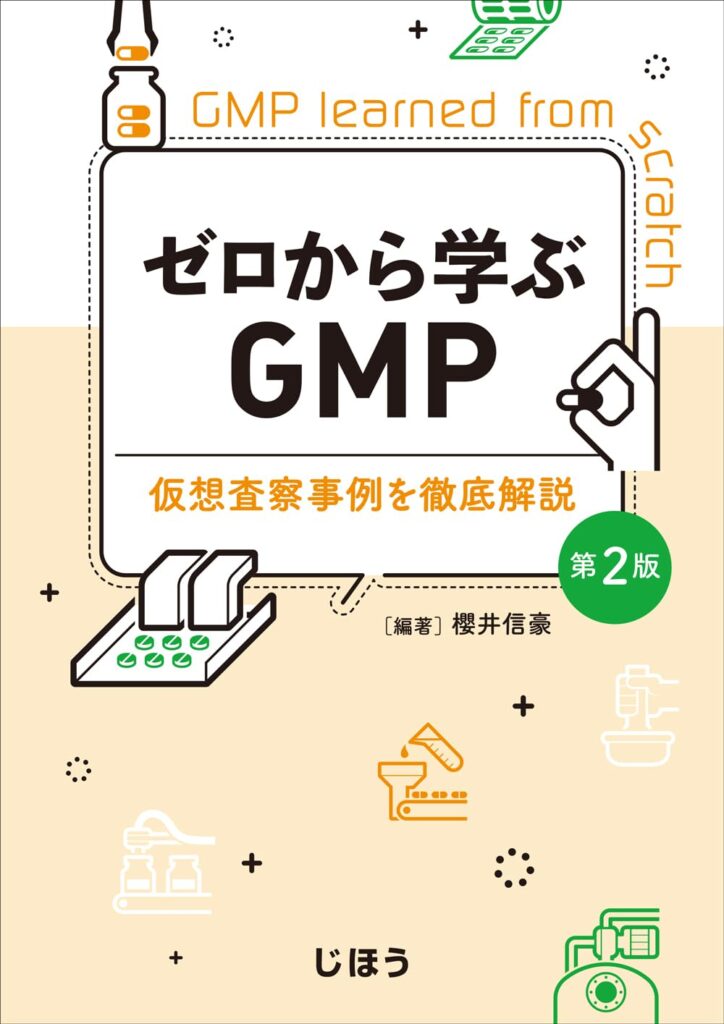

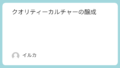
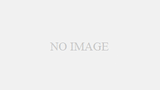
コメント