薬の町と知られる大阪 道修町に行ってきました。
調べて思ったのですが、道修町って結構小さいんですね。

細長い
最寄り駅は淀屋橋駅、北浜駅ですかね。想像以上に区域が狭い印象を受けました。
道修町について
薬の町となったきっかけは堺の豪商小西吉右衛門が徳川秀忠の名により道修町に薬種商を開いたことによるそうです。その後薬種問屋が集まり幕府公認の道修町薬種中買仲間(今で言う組合とかなんとか協会みたいなものでしょうか)が道修町に集められたいろんな薬を検査し適正価格を定めて独占的に供給していたそうです。明治以降、西洋薬が主流になると共同の薬品試験所の設置や制約事業にも着手し、薬どんやから製薬企業に発展していき、現在も薬に関する企業が多く集まっています。
武田、塩野義、田辺三菱、大日本住友などなど現在も続く製薬企業が通りを歩いても目にします。
元々今で言う医薬品卸業からスタートしているというのも意外ですかね。といっても商品を取り扱う⇨品質を保つために試験所作って試験を行う⇨試験のノウハウ集まったから自分で製造しよういう流れは自然なのかもと思います。
なぜ道修町に中買仲間ができたかは推測ですが、このあたりが船場(河川と堀川に囲まれていた場所)dのため、物流の拠点であり、商人が集まっていました。天下の台所というやつですね。人、物が必然的に集まる場所だったからではないかと思います。
道修町の特徴
道修町は薬のまちと言われるだけあって多くの製薬企業が多く、博物館もあります。また通りを歩いていると漢方薬局が2件ほどありました。なかなか他では見ないのですよね。外から見えるように生薬が展示されていた薬局もありました。鹿茸とか猿頭霜とか珍しい生薬もありました。見てるだけで楽しくなってきますね。
https://osaka-chushin.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/museumstreet.pdf
道修町ミュージアムストリートとして案内されています。
大阪中央区のオフィシャルサイトもご覧ください。https://osaka-chushin.jp/news/31448
また、少彦名神社もあります。この時期なので国試の合格祈願でお参りに行かれるのもいいのではないのでしょうか。張子の寅が出迎えてくれます、薬の展示もあります。

あっ道修町に行くなら平日の方が楽しめます。事前に調べて、予定を立てていきましょう。
何も知らず土日にいったら史料館やってないので。(予約いるものもあるので注意)


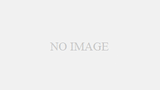

コメント