- 医薬品の製造中止の流れについて
- 製造中止までの流れ
- まとめ
医薬品の製造中止の流れについて
採算が取れない、原料の供給が見込めないなどの理由で製造中止、薬価削除の決定を下す場合があります。ただし、製薬企業側が勝手に中止はできません。医療需要に応えてきた医薬品が製造販売業者の経営事情等に突然供給停止されることは国民医療に重大な支障をきたすことからとされています。
どのような流れで販売中止になるのかを見てみましょう。
製造中止までの流れ
- 代替品の追加供給の確認
まず製造販売業者は、供給停止、薬価削除を希望する品目について、代替品(臨床上の位置付けが同じであれば必ずしも同一成分でなくてOK)を持っている他の製造販売業者にかわりに供給可能か確認し、了承を得ます。
この時、自社の供給量に相当する量を供給することが求められます。
- 学会への連絡、了承
次に供給停止、薬価削除予定品のシェアと代替品について学会に説明を行い、手続きを行うことを学会から了承を得る必要があります。
ちなみに学会は以下の学会から対象品目の使用が想定されるの学会の了承が必要です。(複数関係ある場合はその全て)
日本内科学会/日本小児科学会/日本感染症学会/日本消化器病学会/日本循環器学会/日本精神神経学会/日本外科学会/日本整形外科学会/日本産科婦人科学会/日本眼科学会/日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会/日本皮膚科学会/日本泌尿器科学会/日本腎臓学会/日本医学放射線学会/日本化学療法学会/
日本麻酔科学会/日本脳神経外科学会/日本形成外科学会/日本臨床検査医学会/
日本消化器内視鏡学会/日本胸部外科学会
小児領域など、対象品目が臨床現場において保険適用外で使用されていることを製造販売業者が把握している場合、その使用が想定される学会
他、製造販売業者が把握している、対象品目の使用が想定される学会
ただし、供給停止を希望する品目が代替品があって、過去5年間の平均シェアが3%以下の品目だと学会に了承を得なくて良いとされています。
- 厚労省への連絡、対応
次に了承が得られたら製造販売業者は厚労省に対して代替品の供給の了承、学会の了承を得たことを示す文書をメールで提出します。その後、厚労省から関係学会意見を聴取します。なお、これは年4回、2〜3ヶ月程度の期間をかけて行われます。
- 厚労省の対応結果及びその後の情報提供について
関係学会への意見聴取完了したら厚労省は製造販売業者に対し、医療機関向けに情報提供を行うことを了承します。一方で関係学会から供給継続要望が提出された品目については要望内容を業者へ連絡されるので業者は対応を検討する必要があります。
検討の結果、供給継続するまたは、学会から要望が取り下げられた場合は厚労省へ連絡します
情報提供を行うことが了承された品目については、医療機関へ情報提供を行います。情報提供が完了したと判断した段階において、薬価削除願、販売中止について情報提供した案内文書を厚労省に提出してします。
- 薬価削除願提出後
薬価削除願が提出された品目について、厚労省は関係学会に対して経過措置への移行について意見聴取します。
意見聴取が終わった品目について、中医協へ報告を行い、厚労省は経過措置以降のための手続きをします。
参照した通知を置いときます。12〜14ページの図がわかりやすいかな
https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001285978.pdf
まとめ
流れを見ていただいてわかるかと思いますが、製造販売業者が勝手に販売中止にはできません。
するにしてもいくつかのプロセスを経る必要があり、かつ時間がかかります。
また、関連学会(≒医師)の了解がないと中止できない、厚労省からも意見を求められるという学会の影響力が大きいです。
薬のことなのになんで薬剤師が出て来ないんですか。
そもそも代替品が見つからなければ、申請すらできないということです。まあ、流石にそこまでいくことは稀だとは思いますが。
その場合は、たとえ赤字であっても作り続けなければならないということになります。不採算再算定で薬価上がればいいんでしょうが、年1回だし、必ず上がるものでもないし、上がったとしても採算が取れるようになるかは・・・。
少なくとももっと簡略的に、業者側の判断が通りやすい形にしていただきたいものです。
無理なものは無理ですから。


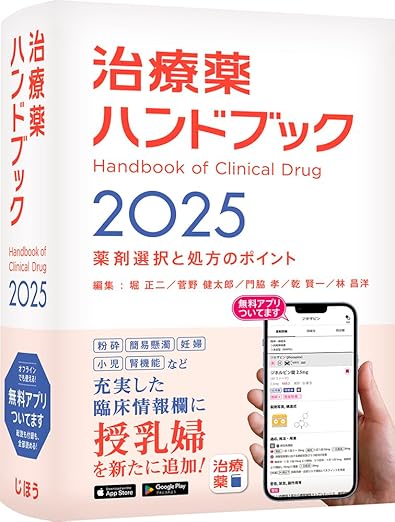
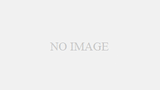

コメント