クオリティカルチャーについては以前記事にしました。
簡単に言えば品質を最優先に考える企業文化のことと言えるかと思います。
クオリティーカルチャーの醸成が必要と言うのは簡単ですが、具体的に何をすればいいんでしょうか。
先日、このことを議題にした県主催の会議(ラウンドテーブル)に参加させてもらったので、振り返りも兼ねて書き出してみます。
クオリティーカルチャーの醸成に必要なこと
・職員の目線の一致
・従業員の意識
・自社品質が自分の大切に思う人に安心して投与できる確証を持てること
・製造している品目の理解
・定期的な教育
・設備導入に伴う架空のバリデーション、SOP作成者の人材
・トップマネジメントの理解、主体性
・トップマネジメントと現場のコミュニケーション
・経営層の考え方の周知
・わかりやすい目標、目標の数値化
・悪い報告しても受け入れてもらえる関係性
・相手の良い行動や成果を素直に褒めることができる
・報連相が活発
現在の問題点
・経営層と現場のギャップ
・必要な人材の不足
・従業員の意識の統一
・教育の形骸化
・経営層やQAが現場に来ないため、現場への理解が足りない
・営業が他部署を知らない
・経営層の判断力不足は現場を知らない、現場からの報連相が不足している。
まとめ
私が参加した班の中にはいわゆる大手の方もいらっしゃたのですが、そう言うところでも同じような悩みをもっていることが印象的でした。規模の大小や製造品目の違いはなさそうです。
議論を進めていくとまず、経営層がどんなビジョン、目標を示しているのか、そこと現実のギャップをどのくらい理解しているのかというのがあがりました。最終的な経営判断を下す経営陣がどこまでGMP、GQPについて、製薬、品質を理解しているかが重要なテーマだと感じました。
ただ、経営陣側に理解してもらうために教育や、現場に来てもらって実際にみてもらうことも必要ですが、現場から声えおちゃんと伝えているか、伝わる環境になっているかは確認しておくべきでしょう。
また、定期的な教育訓練は必要であるという認識は一致していました。
しかし、回を進めるとどんどん形骸化して本当に意味のあるものになっているかという問題も出てきてしまいます。
どうやって実効性を高めるか。例えば毎回定期の教育終わりにテストを行うのも1つの手だと考えられますが、業務内容が違うので、それぞれの業務にあった内容のテストを作る?でもそんな時間はない。といった悩みも出てきます。また、時間がたっていても理解されているかを確認する必要もあるでしょう。いやあ、悩みどころです。
それと、個人的に確かになあと感じたところが逸脱などについてでした。
逸脱が発生した場合報告は必要ですが、逸脱という言葉が負のイメージが強く、特に経験が浅い人ほど言い出しにくいと感じているとのことでした。
確かに、ちょっと言い出しにくい感じはします。逸脱はその後の改善につながるため決して悪い事ではないですがね。まあ、確かに追加で処置をしなければならないので手間が増えるのは確かですが。
ただ、ここで対処していればという話にはなるんですがね。
統一の正解はなく、試行錯誤を繰り返して各社にあった醸成をしていくことが重要であり、常に考えていくことが大事なのでしょうね。
PMDAのラウンドテーブルの資料も参考にしてください。

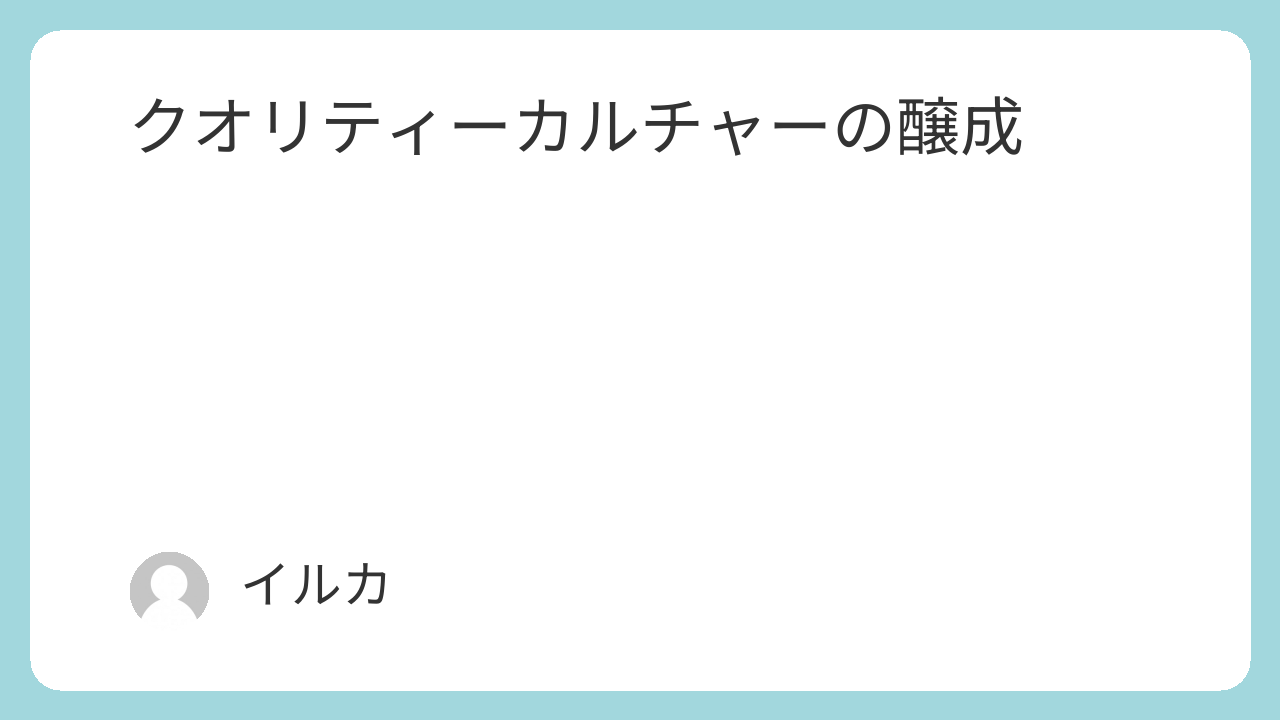
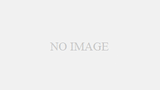
コメント